【公式】YouTubeチャンネル シュタイナー教育講座
YouTubeチャンネルにご登録ください
【公式】YouTubeチャンネルに新しい動画をアップしています。最新動画はこちらをご覧ください。
【シュタイナー教育講座】シリーズ
過去の動画をご紹介します。以降、毎週アップ中です!
(101)「塔は全然高くない!」思春期のわが子からの挑戦 ~中学校1年生の成長段階~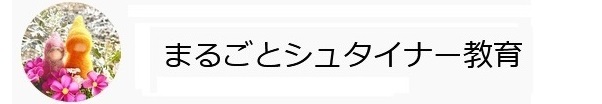
【公式】YouTubeチャンネルに新しい動画をアップしています。最新動画はこちらをご覧ください。
過去の動画をご紹介します。以降、毎週アップ中です!
(101)「塔は全然高くない!」思春期のわが子からの挑戦 ~中学校1年生の成長段階~思春期の子どもたちは自分で自分の考えを持とうと努力をし始めます。 すると、父親の話す価値観に対して全く違うところから意見を言うようになります。自分は父親とは全く違う意見を持っていることを主張し始めるのです。さあ父親は一体、 どのように対応したら良いのでしょう?ぜひご視聴ください!
今回もさらにユーモアを深掘りしていきます。なぜ思春期の成長において、大人のユーモアが何よりも大切なのでしょう。?今回のお話では、大人自身が自分に対してある余裕を持つことで、子供に向かったユーモアたっぷりのアプローチが可能になるお話をしていきます。ぜひお楽しみください。
思春期の子どもたちとのやりとりに、日々気持ちを荒立ててしまう親御さんもたくさんいらっしゃるのかもしれません。今回のテーマは、日常で起こるような具体的な例を挙げて、彼らとのやり取りの「癒し」になる「ユーモア」の真髄についてご紹介します。
6年生ごろのプレ思春期の子どもたちは、突然親と会話をすることをやめてしまうかもしれません。本当だったら会話を通して思考を育んでいく年齢であるのにもかかわらず、大人の前で、彼らは口を閉ざしてしまう傾向にあります。いったいそれはなぜでしょう?そして今回は、どうしたらわが子の思考の力を引き出す会話をしていっていけば良いのか?についてお話をさせていただきます。
6年生ごろのプレ思春期の子どもたちは、突然親と会話をすることをやめてしまうかもしれません。本当だったら会話を通して思考を育んでいく年齢であるのにもかかわらず、大人の前で、彼らは口を閉ざしてしまう傾向にあります。いったいそれはなぜでしょう?そして今回は、どうしたらわが子の思考の力を引き出す会話をしていっていけば良いのか?についてお話をさせていただきます。
12歳頃の子どもに心身ともに大きな変化が現れます。そのことに対して、私たち大人が気づかないと、子どもたちは徐々に自分の心を閉ざしてしまうかもしれません。今回は新しく変化した我が子に気づくためには、いったいどのようなことが必要なのかお話ししていきたいと思います。
11歳から12歳にかけて思春期の子どもは大きく変化します。今回はこの年齢の成長に焦点を当て、「一体子どもたちの中でどんな変化が起き、そのことによってどんな新しい能力が誕生したのか?」ということについてお話ししていきたいと思います。
今回は、シュタイナー教育の観点から人間の人生について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。自分の中に主題テーマがあるとしたら、それは一体どんな響きを持っているのでしょう?今回はベートーベンの悲愴の楽曲第二楽章の主題テーマをもとにして、人間の人生について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
「褒めるとは包み込むこと。」今回のお話ではさらに褒めるということを深掘りしながら、子どもの成長の中で、大人のどのような言葉や働きかけが彼らの人生の糧になっていくのかということを、多角的な観点からお話しさせていただきます。
今までは褒めることについてお話をしていきましたが、今回はそれ以上にもっと大切な「励ます」というテーマについてお話をさせていただきます。親が子どもに対して励ます姿勢の中に、一体どんな魔法の力が入っているのでしょうか?子どもの未来にとって必要な力についてお話をさせていただきます。
今回は甘えと褒めるの関係についてお話をしていきたいと思います。子どもの中にある力を引き出してあげるためには、大人の声掛けがとても大切になります。今回は70年代に注目された「甘えの構造」を例にとりながら、大人のとても大切な子どもの導き方についてお話をさせていただきます。
大人は、一体子どもの何について褒めてあげれば良いのでしょう?今日は子どもを褒める褒めないという考えの前に、子どもを注意深く観察してあげることで、彼らの中の大きな能力を引き出してあげるお話をしていきたいと思います。
「褒めて育てる」ことに対して、ここ数年議論されています。 今回はシュタイナー教育の観点から、子どもを褒めることの本当の意味について、お話ししていきます。また、子どもは深いところで何を親に求めているのか、ということについて一緒に考えていきたいと思います。
呼吸と脈が整う5年生の心と体に調和が訪れます。 この時期を逃さずに、様々な興味を子どもの中に目覚めさせてあげましょう。今回は具体例を挙げて、一体どのような形で子どもが学びに対して心を開くのかお話しします。
私たち大人は、誰もが子どもの中の能力を豊かに引き伸ばしてあげたいと願っています。その中で現在一般的に子どもに使用されているスマートフォンの与える影響を今回のテーマにしていきたいと思います。とても便利だからこそ、一体どのような負担がこの年齢の子どもにもたらされるのでしょうか?そしてどのような意識を持ったら、この時期の子どもの成長を損なわないやりとりができるのでしょうか?今回はそのことについて皆さんと一緒に考えていきましょう。
Microsoftの創業者であるビル•ゲイツ氏が、我が子をメディアから遠ざけていた話は有名です。シリコンバレーのIT系企業経営者がシュタイナー教育を選ぶことは、すでに10年前から知られています。Googleのマネージングディレクターであるアラン・イーグルは、娘をカリフォルニア州のシュタイナー学校に通わせています。雑誌「タイムズ」のインタビューでは、「iPad上のどのアプリでも、私の子供たちに人間の教師よりも優れた読み方や計算を教えることができるという考えはばかげている。」と答えています。(雑誌教育芸術2012年5月号)
すでに10年前から、アメリカのシリコンバレーで活躍するIT系企業経営者たちが子どもをシュタイナー学校に通わせていると言う事は、よく知られている話です。最先端のIT技術を扱っている彼らが、なぜそのテクノロジーを自分の子どもに早いうちから触れさせないようにしているのか?今回はその理由について深掘りしていきたいと思います。さらに、なぜシュタイナー教育では、できるだけテレビやYouTubeなどを中学生まで遠ざけておくのかと言う事を詳しく紹介するだけでなく、その代わりに子どもたちが育んでいける最高の力についてお話ししていきたいと思います。
シュタイナー学校では、演劇の取り組みをとても大切にしています。なぜなら演劇を通して学ぶことがとてもたくさんあるからです。特に学級の中でいざこざがあった時、劇の取り組みは、子供たちの間に大きな癒しをもたらすだけでなく、肯定的に人と繋がれる純粋な意欲を子供の中に目覚めさせます。いったいそれはどうしてでしょうか?今回はそのことについてお話をさせていただきます。
11歳の子供は何に対しても感動できる力を自分の内側に持っています。それは一体なぜでしょうか?子供の身体の中に起きている大切な成長の過程を、一生の力として育んでいくことができます。それは一体何でしょうか。今回はそのことについてお話をさせていただきます。
5年生の子供の呼吸と脈の関係は、私たち大人と同じ1対4の関係になります。この成長期に様々なリズムをオイリュトミーの中で動くことによって、成長する子供の心と体に大きな調和がもたらされます。呼吸と脈が整うときに、なぜオイリュトミーがとても大切な取り組みになるのか?今回は5年生の成長とオイリュトミーの関係についてお話をさせていただきます。
シュタイナー学校では5年生でオリンピックの競技を行います。今回はオリンピックの始まりとその意味についてお話しさせていただきます。なぜこの年齢の子供たちが「古代ギリシャ人か」という謎が、オリンピックの原点を理解することで解かれていくでしょう。
今回は5年生の成長段階において、呼吸と脈の関係からスポーツ及び体育全般について考えていきたいと思います。現在、とても大切なスポーツ競技はシュタイナー教育の観点から、一体どのように見えるのか、一緒に考えていきたいと思います。
5年生は調和を愛する心と体を持った素晴らしい成長期です。今回は、この年齢の子供たちの心と体に一体何が起きているのかを呼吸脈白の観点からお話をし、そこから彼らの成長にとって何が大切かをさらに皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
今回は10歳の子供の成長とお小遣い、いわばお金について皆さんと一緒に考えていきます。周りに向かって目覚めた意識を持った10歳の子供が、一体お小遣いとどのような関係を持っていけば良いのでしょう?そしてどのような取り組みの中で、子供が本当の意味でモノやお金とつながっていけるのでしょうか?今回はそのことについてお話ししていきたいと思います。
10歳が興味を持つと、彼らの人生がますます豊かになる! 個性が生まれ始めた10歳は、自分の中の特別な興味に目覚めます。生き物、芸術、技術など様々な方向に子どもの興味の羽が羽ばたきます。なぜそれが子どもの人生にとってなくてはならない宝なのでしょうか?今回はそのことについてお話しさせていただきます。
強い個性が表れ始めた4年生から、その子に合った楽器を習わせてあげることは、子どもの中の計り知れない能力を引き出します。なぜ楽器演奏が人間の成長において、大きな力になるのでしょうか?今回はそのことについてお話しします。
子どもの意識が目覚める10歳では、誕生日に特別なプレゼントを贈ることができるでしょう!そのプレゼントとはいったいなんでしょうか?そしてなぜそれが子どもの人生にとって大切な贈り物なのでしょうか?今回はそのことについてお伝えします。
子どもは10歳になると、自分の中に新しい個性が誕生するのを感じます。もし周りの大人たちが子どもの中に誕生した「新しいその子」に気づくことで、子どもの一生の人生ある大きな力が生まれます。それは一体何でしょう?今回はそのことについてお話をさせていただきます。
兄弟姉妹たちは意味があって、この順番で生まれてきたと言えるかもしれません。今回は以前に紹介した「兄弟関係」のテーマをさらに深掘りして、両親がどのように兄弟と取り組んだら、兄弟関係が良くなっていき、彼らが安心してすくすくと成長していくのかということについてお話ししていきたいと思います。
子どもを育てる環境の中で、我が子の前で夫婦喧嘩が起こるのは日常茶飯事と言えるのかも知れません。それではいったいどのように喧嘩の後フォローすれば、子どもの中で深い傷にできるだけならなうにでしょうか。今回はそのことについてお話しします。
4、5年生の子どもは自分から意欲的に友だちを探し始めます。いったい子どもたちの中に何が起きているのでしょう?そしてどんな取り組みをしたら、後に他者とやり取りできる、安定した人間へと成長するのでしょうか?今回はそのことについてお話しします。
かけがえのない子ども時代は4年生から5年生です。この時期をシュタイナー教育では「子ども時代の真ん中」「子ども時代のクライマックス」と言います。一体この時期にどんなことをすれば、思春期になっても子どもは健やかにすくすく成長できるのでしょうか?今回はそのことについてお話します。
4年生の子どもは、目覚めた意識で周りの世界とつながります。だからこそこの時期に地域に根付いた食文化を子どもに伝えていくことは大切です。更に親が大切にしている味覚を伝承していく事も、この年齢の子どもの成長にとって欠かせない宝となります。一体なぜでしょう?今回はそのことについてお話をさせていただきます。
目まぐるしく変化する、この時代だからこそ、時間をかける取り組みが、子どもの人生にとって一生の宝になるでしょう。今回は具体的に家庭の台所でできる実践的な内容を例に挙げながら、この年齢の成長を支える取り組みを紹介します。
日本の中に根付いている二十四節気や七十二候は、日本人にとって生活に欠かせない暦です。春は桜、梅雨は紫陽花など暦を生活の中に取り入れていく事は、とても大切なある力を子どもの中に育んでいきます。今回はそのことについてお話をさせていただきます。
情操教育が1番大切な3年生から4年生の子どもたちにとって、四季折々の催事は重要な取り組みになります。今回は「もういくつ寝るとお正月。。。」の意味を深めながら、四季の取り組みの中で、子どもがどのように生きる意味を見つけていくかをお話ししていきます。
10歳の子どもの自然体験は一生の宝物です。子どもの内側が目覚め、同時に感受性が豊かな、この時期に自然界での深い体験をすると、子どもの中に一生何かを探求していく意欲が湧いてきます。今日はそのお話をしていきたいと思います。
10歳の子供たちは、日常生活のシンプルなものにとても大きな興味を示します。手を使う大人たちの動きだったり、何かを作る姿勢だったり。それ以外にも動物の話を聞くだけで、10歳の子供たちは心がワクワクします。今日は10歳の子供の内側のやる気を引き立たせる内容をお伝えします。
この世界は10歳の子どもにとって初めて自分の故郷になりました。一体どのようにしたら、この故郷の中で子どもが思い、存分、自分の中にある能力を発展させていくのでしょうか?今日は声かけと子どもの意欲の関係についてお話をしていきます。
10歳の子どもたちの目は、外の日常世界に向いています。メルヘンの世界ではなく、日常生活が彼らの新しい領域です。その中で、私たち大人はどのように子どもと取り組んでいったら良いのでしょうか?どのようなやりとりをしたら、子どもの中から大きな意欲が湧いてくるのでしょうか?今日はそのことについてお話しします。
目覚めた意識で世界を見つめる10歳の子どもたちにとって、一体どんな学びが大切になってくるのでしょう?今回はデジタルメディアを使わずに子どもワクワクさせるさまざまなアイデアをご紹介いたします。
10歳の子どもはもうファンタジーの世界でまどろんではいません。彼らのフィールドはこの現実世界です。だからこそ、彼らが育った地元と様々な活動を通してつなげてあげて下さい。今回はその深い理由についてお話ししていきます。
4年生の子供はとても大きく変化します。成長で言えば放物線のような成長です。子供の中の意識が変わり、対人関係にも大きな変化が現れてきます。今回はそのことについてお話をさせていただきます。
なぜ子どもは、子ども同士の間で、または私たち大人の前で嘘をついてしまうのでしょう?彼らの中に一体何が起こっているのでしょう?嘘をつく子どもを叱るだけでなく、嘘をつく子どもの心の中を一緒に見つめてみましょう。今日はその話をしていきたいと思います。
シュタイナーは9歳の子どもが大人に認めてもらえないと大きな危機にさらされてしまうと警告しています。それは一体どういうことでしょう9歳の子どもの中で一体何が起こっているのでしょう?そのことについて今回はお話をさせていただきます。
子どもは本当は大人にどのように接してもらいたいのでしょう?慌ただしい毎日の中で時間のある時、次のことを行うと子どもはとても安心するでしょう。9歳にとって大人がプレゼントしてくれるものは信頼関係という土台です。
9歳の子どもの瞳はまっすぐ大人に向かっています。彼らが求めているのは、私たちの中にある本当の気持ち。そして正直な心。私たち大人は、間違った時に子どもに素直に謝れるでしょうか?または少しはぐらかしてしまうでしょうか?9歳に向かって誠実でいる事は、子どもを幸せに伸ばすことなのです。
9歳の心は大人にとてもシンプルなものを求めています。「どうしてそれをするの?どうしてそれを言うの?」です。 いったいその心の願いに私たち大人はどのように応えていけば良いのでしょう?
9歳の壁に差し掛かった子どは、今まで条件なしで尊敬していた大人を問い始めます。大人は本当に尊敬に値する人物なのか?この年齢の子供たちは、以前のように無条件に私たち大人に何でも懐いてくるのではありません。それではいったい子どもの内面でいったい何が起こっているのでしょうか?
9歳の子供たちはメルヘンの世界から去って行きました。そして日常世界が子供たちの大きなテーマとなります。それでは一体どんな日常生活の取り組みをしていくと、小学校3年生の子供たちはこの世界の中にしっかりと根を下ろすことができるのでしょうか?今回はそのテーマについてお話をしていきたいと思います。
3年生の子供たちの心を癒す物語は〇〇です。ファンタジーに包まれていた幼少期の時代から9歳の子供は離れ、新しい時代へと進んで行きます。その過程の中で、子供の内面がとても不安定になる時、子供を支えるとても素晴らしいお話があります。今回はその物語についてお話をしていきたいと思います。
自分の中で自意識を持ち、外の世界を批判し始める子供の心の中に一体何が起きているのでしょう。場合によっては日中と夜寝る前の子供の振る舞いが大きく変わる場合があります。今回はそのことについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
9歳の子供の中に大きな変化が起こります。それは子供自身が今まで自分自身を優しく包んでくれていた世界から離れていくことです。そして徐々に自分自身をしっかり持つようになるのです。それは、大人にとっても、子供自身にとってもとても容易なことではありません。今回は、一体子供の心の中に何が起きているのかと言うことを中心に、9歳の壁と言うテーマについて、お話ししていきたいと思います。
子供たちは私たちの中に一体求めているのは何でしょう?私たちの心の奥底に潜むもの。まさにこれを子供たちは私たちに求めているのです。今回の動画は、一体それが何かということについてお話をさせていただきます。
2年生の子どもたちは大人の言葉に鋭く反応します。自分に対して大人が本当にそう思って言ってるのか、または体裁だけで行ってしまっているのか。この年齢の子どもたちはとても敏感です。大人の子どもに向けたメッセージについてお話をさせていただきます。
シュタイナー学校で演劇をすると言う事は、とても教育的な行いです。なぜならば、生徒一人ひとりの中にある言葉の力を引き出す取り組みだからです。今回の動画は、なぜ劇を通して子供の内面が強くなるのかということについてお話をしていきたいと思います。
2年生は一年生の頃とは少し異なり、自分の中に幾分目覚めが生じる学年でもあります。友達とのトラブルが多い理由は、実はこの自分自身が目覚めたことにその原因があるからです。この動画では、子供の内面に生まれた2つの異なった目覚めについてお話をしていきます。
ルドルフシュタイナーは、人間には4つの気質があることをシュタイナー教育の1番初めに提唱しました。大人として教育者としてこの気質に取り組んでいく事は、子供を深く理解していく大切な糸口となります。今日はこの気質の最初の入り口をお話しさせていただきます。
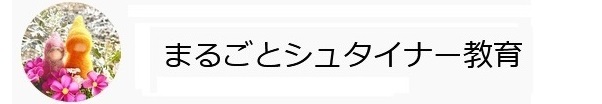

本校を卒業して10年以上が経ち、久々に学校を訪れてみると、改めて賢治の学校の生徒の凄さを知りました。
子供たちの未来の為に役立てることを考えた時、再びこの学校に戻ることを決めました。
一人ひとりの才能や可能性、夢を守ること! そしてそれを全力で応援します!
Schubert:Sonate für Klavier Nr.21
(シューベルト:ピアノ・ソナタ21番)
シューベルトは命の恩人です。

本校の卒業生です。卒業後ドイツシュトゥットガルトユーゲントゼミナールを経て、東京藝術大学で美術を学び修士課程を修了後、講師として戻ってきました。
一つの作品やテーマを深めていくことは難しいことです。そこへ真剣に挑む生徒たちに誠実に向き合いたいです。

国立市の天下市で、娘をベビーカーに乗せながら七頭舞を見たのが最初の出会いです。個性的な若者が美しく舞う姿とシュタイナー教育という言葉が心に残っていました。数年後、娘がご縁をいただき入学。公立学校で特別支援教育に携わりながら鳥山先生の書籍や教員養成講座で学ばせていただく中で、この学校にもっと関わりたい気持ちが膨らんでいきました。
様々なバランスを取ることです。子どもの見方や関わり方が偏っていないか、小さな声も聞けているか、今必要なことは何か、など。
BIGBAND JAZZ(count basie orchestra)
藤井風
久石譲
学生時代はマーチングバンドやビッグバンドでアルトサックスを吹いていました。

横浜シュタイナー学園を卒業した我が子が進学先として選んだのが本校でした。
毎日保育を振り返り、チームとして「子どもたちにとって、より良い環境」となれるよう、考え動いていくことを一番大事にしています。
その為にも、真っ直ぐな気持ちで誰とでも関われるように心がけています。
息子がフルート、娘がチェロを弾くので管弦楽が好きです。
特にエルガーの「威風堂々」(とにかく華やかで気持ちがスカッとします)。
そして、高等部生徒による合唱(毎回、心が洗われ、涙が出るほど感動します)。

2004年に1年生として入学し、12年間この学校で学びました。
何事もとにかくまずはやってみることです。ここへ来る前は農業界で働いていましたが、高等部の頃は1.5tトラックにフォークリフトで積載量いっぱい荷物を積んで走れるようになるとは思っていませんでした。
この学校で出会ったオキクルミと悪魔の劇の歌、母のよく聴いていたマーカス・ミラーのベース、ピアノで取り組んだブラームスやベートーベンの曲、家で聴くササノマリイさんの曲、などです。

鳥山敏子先生の著書を図書館で見つけて読んだことが、一番初めの出会いです。
誠実に向き合うことです。
好きな音楽はたくさんありますが、そのなかでも、バッハの音楽にとても惹かれます。

大学の教育学部時代に鳥山敏子さんの本に出合いました。子どもに対する見方の本物を彼女が語っていると感じ、彼女のワークショップに参加してからこの学校との関わりが始まりました。2003年には教員養成ゼミナールをドイツで一年受け、この学校の教員になりました。
常に正直にまっすぐに子どもに向かうこと、そして子どもを良く見聞きしわかること、です。
子ども時代の曲ですが、アタックナンバーワンや科学忍者隊ガッチャマンを聴くと元気が出ます。そしてブルーハーツも好きです。

ドミニカ共和国で青年海外協力隊として働いているときに、シュタイナー教育について知りました。そして日本にもシュタイナー学校があると聞いて、インターネットで調べたら賢治の学校のホームページが出てきました。そこから2003年に教員養成ゼミナールがドイツで一年間日本語通訳をつけて開催されると聞き、すぐに問い合わせたらもう締め切りぎりぎりになっていました。どうしてもということで賢治の学校を訪れて面接し、ドイツ講師が来ている夏のゼミナールに参加後、即決でその秋にすぐドイツに向かいました。そこからずっと担任として日々子どもたちの育成に関わっています。
人間として正直に、誠実に生き、しっかりと子どもの前に立ちたい思います。そして子どもの未来の可能性にも目を向けながら、子ども全体が大きく成長していけるために、日々子どもとのやり取りを大切にしています。
スペイン語のポップです。例えば「MORAT」というスペインで活躍しているコロンビア人のバンドグループが好きです。

大学卒業後、教員免許を取るための学びをしながらアルバイトをしていた先で、この学校の生徒と出会いました。当時12年生だった彼の人との接し方、調和的な姿に驚き、シュタイナー教育に関心をもちました。そして、彼のお母さんからこの学校を紹介していただき、オープンスクールに訪れたのがこの学校との出会いでした。それから約3年の研修を経て、この学校の教員になりました。
振り返りをすることです。子どもとの関わりから今日は何を学び、明日をよりよくするためにはどうするのか考えること。日々成長していきたいと思っています。
BUMP OF CHICKENです。

一番初めは私が月一回逗子で開催していた「モダンダンスを海辺で踊る会」に賢治の学校横浜事務局の男性が来ていて、そこで鳥山先生の上映会をやっているのを聞きました。その上映会に顔を出したのが鳥山敏子と最初に出会った日です。その後賢治の学校の横浜の集まりに私が顔を出すようになってから、横浜の事務局をやらないかと話を持ち掛けられました。初めて逗子でのなんと2週間にわたる鳥山敏子の全国大会を開催しました。そして全国での賢治の学校の催しに参加し、まさに学校づくりの現場の真っただ中にい続け、活動してきました。その場でも子どもたちに向けてのワークショップを行い、1998年に最初の一年生が入学して以来今まで、賢治の学校の子どもの育成に関わり続けています。
「建前と本音」ではなく、生徒の中の内側で動いていることと、外側に現れることが、いつも一致しているように、彼らが自分を素直に表現できるように関わっています。なぜなら正直であるというところから、人間は真の強さを生み出すからです。
私自身も自分らしくありながら子どもとしっかり向き合う。日々、心がけていることです。
バッハのゴールドベルク変奏曲です。しかもピアニストの巨匠グレン・グールド演奏で。

創設者鳥山敏子先生が書かれた本を大学生の時に読み、彼女の授業に興味を持ちました。その後鳥山先生が公立の学校をやめられたと聞いて、その年に鳥山先生のワークショップに参加しました。その時子どもの前に立つ教師として自分が取り組まなければいけないことがあると気づき、賢治の学校と関わり始めました。その後ドイツ教員養成ゼミナールを卒業し、東京賢治シュタイナー学校のクラス担任として、子どもたちの育成に関わっています。
子どもの中に何が育っているのか見つめる目をもつことです。そしてその子が成長していくことの支えになる授業や日々の取り組みをとても大切にしています。
パッヘルベルのカノンです。自分の行く道を応援してくれるような素晴らしい力をいただける曲です。

2002年1月、彫刻家として活動していた当時、個展のダイレクトメールを作るために訪れた印刷会社のそばのお店に賢治の学校の「教員募集」のちらしがありました。そのころ、シュタイナー教育こそが自分のやりたかったことではないかと思い始めていた時で、すぐに連絡を取り、3日後に東京賢治の学校に面接に訪れました。そこで初めて鳥山先生を知りました。そして一か月後にヘルムート・エラー先生の講座を通してこの教育の素晴らしさを改めて実感し、そのまま4月から娘の編入とともにこの学校の教員になりました。
その日を振り返って、子どもはあの時本当は何を言いたかったのかな。自分はその子の声をちゃんと聞けたのかな。と自分に問い、改めて心の中で話しかけるようにしています。子どもの内なる声に沿って、自分を改めていけるようでありたいと思います。
ブルースです。ジミ・ヘンドリックスの「エンジェル」は好きですね。それからオーティスレディングも好きです。
あとはケルトの音楽やカタロニア民謡は懐かしさが湧いてきて好きです。

東京賢治シュタイナー学校に子どもを通わせていた親の方からこの学校の存在を知りました。初めは学童にボランティアで関わっていましたが、シュタイナー教育の素晴らしさを感じ、徐々に教師になる決意を固めていきました。
愛する子どもたちに正直にまっすぐに向かうことです!
サザンオールスターズです。

1988年にドイツのユーゲントゼミナールに入学しました。その後ミュンヘンのオイリュトミー学校を卒業し、1993年に日本でのオイリュトミー卒業公演をしました。その後ニュルンベルクのシュタイナー学校でオイリュトミーの教師とオイリュトミー舞台グループ「フィオーナアンサンブル」の活動をしながら、毎年日本とドイツのワークショップを開催することで賢治の学校設立運動をサポートしてきました。その後2001年から3年間ドイツニュルンベルクでシュタイナー教員養成ゼミナールを開催。その後賢治の学校高等部設立でさらに年4-6回来日する中でついに2007年に夫ヴィリギリウス・フォーグルと共にこの学校に招かれ、意を決し帰国。現在に至ります。
豊かな精神に満ち溢れた子どもを見る眼。
限りない可能性を持った子どもという宝の前に常に畏敬の念を抱くこと。
夫が演奏するフルートの曲。

ドイツミュンヘンの大学で物理を学んでいるときに、ミュンヘンのオイリュトミー学校で一人の日本人の女の子に恋をしたのが賢治の学校とのはじまりです。1993年に日本でのオイリュトミー公演を彼女と行った後、ドイツニュルンベルクのシュタイナー学校で教鞭をとりながら、14年間の間に20回以上彼女とともに来日し、シュタイナー教育とオイリュトミーを東京賢治シュタイナー学校に伝え続けてきました。そして2007年についにこの学校の教師として教師会から日本に招かれることになったのです。
子どもたちの輝く目です。私の宝物です。
フルートの曲すべて。フルートは私の存在の一部です。どんなに忙しくても日々の練習は欠かしません。

北海道の中学校教員時代、太郎次郎社の教育雑誌「ひと」を毎月読んでいました。当時「ひと」の編集代表を鳥山敏子先生がしていたこともあり、そこから彼女が主催する様々なワークショップに参加し始めました。それがこの学校につながっていったといえるでしょう。そして賢治の学校が立ち上がる1999年に北海道からパートナーと共に引っ越し、私は賢治の学校の大人クラスに入学しました。
常に自分が生徒一人ひとりに何が必要なのかを知るために、日々心の耳を研ぎ澄ましています。
合唱音楽! 特にルネッサンスの宗教音楽です。

2人の子どもを育てているうちに鳥山先生の作った賢治の学校の雑誌に出会いました。そこからシュタイナー教育の素晴らしさを知り、すぐにこの学校に子どもを通わせたいなと思いました。それから一年くらいかけて夫と話しあいを繰り返し、イベントに参加し続けました。そしていよいよ最初の賢治の学校の一年生の親として、入学式を晴れやかに迎えました。新一年生はわずか2人でした。その後さらにシュタイナー教育の内容を深く学び、自分自身も教師になる決意を徐々にしていきました。
教師の立ち姿が子どもにとっては重要と考えています。私自身手仕事を愛しているので、生徒たちにそのすばらしさを伝えていくのがとても大きな喜びです。子どもたちはとても器用な手を持っていて、手から様々な芸術作品が生まれています。
声質の良い歌。綺麗な声のマドレデウスとかです。現代ではスピッツの歌声。美しい声が特徴の来生たかおとか沢田研二も好きです。

立川で鳥山敏子先生の講演を聞いたことが最初の出会いです。
子どもたちのために子どもたちにとって大切な時間を過ごせるように、日々心がけています。
カヴァレリア・ルスティカーナです。

東京賢治シュタイナー学校の一期生の親の方が営むシュタイナーの幼稚園で働いていたとき、この学校を紹介されました。そしてドイツ講師の講演会に訪れたことが最初の出会いです。
古くならない、今の時代に合ったシュタイナー教育を常に目指していることです。
日本のポップスです。特に星野源さんの「SUN」です。

90年代の初めに鳥山敏子先生の茨城大学のワークショップに参加したのが始まりです。そのあと賢治の学校に興味を持ち、全国大会に参加した後、賢治ゆかりの花巻をツアーで訪れました。そして鳥山先生が作った「孫悟空」の上映会をすることで、賢治の学校茨城地方事務局を立ち上げました。その後東京立川の賢治の学校で幼児部を設立することを聴き、幼児クラスの設立からこの学校運動に深く関わっています。
やさしく温かいぬくもりの中で、子どもが安心する確かな導きを行うことです。
仕事でも日常でも童謡が大好きです。なによりも愛している曲は「ドングリコロコロ」です。

秦先生とオイリュトミーの舞台活動をしている時、秦先生に誘われたのが始まりです。そして、子供の入学を機に関わり始めました。
自分が学び続けることで、人や物事の中で信頼を持って成長していく過程を大切にしています。
バッハ
The Rose

子どもをシュタイナー教育で育てるため。
心穏やかに待つこと。
リベル・タンゴ
わらべ歌

自分の子どもをシュタイナー学校に入れたいと思い、学校を探していましたが、自分が教員の仕事をしていたので学童があるこの東京賢治シュタイナー学校を選びました。そしてその後、この学校の高等部の英語教師のお誘いが来ました。
日々自分がいろいろな意味で学び続ける人間であることです。
クラッシック音楽です。バッハの曲が好きです。
そしてRCサクセションの曲も好きです。

学生の時、鳥山敏子先生の描かれた書籍や太郎次郎社の教育雑誌『ひと』を読んでいて、敏子先生のお考えに触れる機会を得ました。子育てをする中でシュタイナー教育に出会い、本を読んだり、自分でできることを実践したり、出られる講座に参加してみたりする中で、その奥深さ、すごさに驚嘆しました。そして、子どもの小学校入学を機に、この学校と具体的なかかわりがはじまりました。
「センス・オブ・ワンダー」(美しいもの、未知なもの、神秘的なものに目を見はる感性)です。この世界のよろこびや神秘など子どもと一緒に再発見し、感動を分かち合えるようになりたいと思っています。
神奈川県立近代美術館鎌倉館が閉館する時に流す曲が好きです。吉村弘さんが作曲したものだそうです。「夕闇が降りてきて、高い空に気流が遠くに響き、家々に明かりがともっていくような愛らしい繊細なオブリガートに飾られた『鎌倉 閉館の音楽』

二人の子どものための学校を探す中で、妻の知り合いがリストアップして渡してくれた学校の一覧がありました。その学校一覧の一番上にあった学校が賢治の学校でした。早速見学に来たところ、ちょうど鳥山敏子先生の授業で、子どもたちののびのびした歌声と、彼女の描いた水仙の絵にとても感動いたしました。そのあとはほかの学校を見ずにこの学校に二人の子どもを入れようと決断しました。
私自身も実際に教師研修や講座を通して、この学校の教育に感銘を受け、大学の教授をする一方、数学の教師としてこの学校を支え続けてきました。
生徒を心から尊重することです。
モーツアルトの交響曲41番「ジュピター」です。そしてショパン作曲のバラードの一番です。

まだ大学生だった22歳の時に鳥山敏子さんのワークショップに参加しました。そこで彼女が学校をつくると呼びかけたので心が動き、その最初の設立運動からずっと関わり続けてきました。そのうちに事務局を任され、賢治の学校の事務を一括して引き受け、賢治の学校の土台を築き上げてきました。
教師として正直で常に誠実であること。日々子どもの中に何が生きているのかを感じながら大地に関わる命の授業を作り上げています。
モンキーマジックです。

私はこの学校を鳥山とつくったので鳥山敏子との出会いを話します。1976年演出家の竹内敏晴さんを訪れたとき、「からだとことばの会」の中で鳥山敏子と出会いました。その後竹内敏晴氏のレッスンを彼女と共に受けていき、彼女の生き方に深く共感し、鳥山敏子の「教師のワークショップ」を彼女と共に開催しました。
その後彼女が学校をやめることになり、賢治の学校づくりを一緒に始めました。そのときはまだ建物は持たずにワークショップや講演会を開催し続けていました。その運動が賢治の学校運動になり、「星の数ほど賢治の学校を」というキャッチフレーズで私も精力的に活動していました。その後長野県の美麻に若者のための賢治の学校を鳥山さんと設立しました。美麻の学校はドイツの「ユーゲントゼミナール」を見本とし、若者の全寮制の学校で一年半続きました。
そしてその後東京の立川の今の前身である賢治の学校に移り、初めは若者と大人のためのクラスをつくりました。でそのうちに子育てに悩む親たちが集まり、幼児クラスを設立しました。さらに小学生もいたので幼児が5人くらいと小学生が2人での学校が開校されました。そのあと子どもたちのための学校ということでオイリュトミストやシュタイナー教育者をドイツから招き、皆で一生懸命学び始めました。そしてその学び続けた流れが今、ここにあるということです。今現在私は、この学校の演劇専科の教師として活動しています。
演劇なので、とにかく一人一人が言葉をしっかり話すこと(もっというと放つこと)、そして言葉を通して人とちゃんと関わっていくことをまず大切にしています。ドラマが生まれてくるプロセスの前提条件だからです。
ジャズです。何よりもビル・エヴァンス!

陶芸家の仕事から自然農の活動に切り替えたころ、自然農を通してこの学校と出会いました。そして当時の賢治の学校の「大人クラス」に入り、それ以来この学校に関わり続けています。
私は陶芸専門なので、まず高等部の生徒に陶芸の技術は教えます。しかし生徒の創造性も大切にし、やり取りしながら生徒の中にある芸術性を引き出すよう心がけています。
ビートルズです。何よりもビートルズ!

創設者の鳥山敏子先生に小学校時代受け持たれました。その関係から「ブタまるごと一頭食べる」の授業や今本になっている様々な実践授業を生で体験しました。その後、日本の音大を卒業後、鳥山先生の娘夫婦の紹介でドイツの音大に留学しました。そこではオイリュトミーの伴奏の仕事を引き受けながら、音楽大学のマイスターコースを卒業。そしてドイツ国内で演奏活動を続けました。その後帰国してからは子供を産み、小学校に上がるときわが子を東京賢治シュタイナー学校に通わせることを決意。そしてほぼ同時に音楽教師の仕事をこの学校から依頼され今日までに至ります。
「丸裸でつくる場づくり」です。
ベートーベンです!彼のすべての曲!

創設者鳥山敏子が開催した全国大会に参加しました。そして初期の賢治の学校の立ち上げに関わり、オペレッタ孫悟空の公演も、共につくりあげました。そこからずっと子どもたちに音楽の素晴らしさを伝えながら、賢治の学校と共に歩み続けています。
何よりも音楽を通して子どもたちが共に深くつながることです。音楽は人と人とをつなげる素晴らしい宝です。
人と一緒に音の会話ができるアンサンブルが大好きです。

子どもの入学を通してこの学校と関わり始めました。同時に高校の数学の教師をしていたので子どもの入学を機にこの学校の高等部数学教師としてもスタートしました。
子どもたちが積極的に授業に関わることです。数学の課題を受け身にならず、自分の頭でしっかり考えるよう常に生徒に働きかけています。いわば全員マックス参加の数学の授業です。
サンボマスター「可能性」です。

東京賢治シュタイナー学校でドイツベルリン教員養成ゼミナールのシュミットライトナー氏の美術の研修を美術講師として受けたのがこの学校との出会いです。それがご縁となってこの学校の高等部の美術教師のお誘いを受け、それ以来高等部の生徒たちと関わりが始まりました。
子供の本質を『観る』ことです。
中世の音楽です。そしてロックも好きです。ロックはクイーンですね。

大学時代、鳥山敏子先生の教育を学ぶ機会に恵まれ、そこで彼女を知りました。その後、鳥山先生が学校をやめて活動していることを風のうわさで聞いていました。しかしある日ある時日野に引っ越して来まして、隣町の立川でなんと鳥山先生が賢治の学校を設立したと知り、驚きました。その後娘と体験授業に参加し、生き生きわくわく、驚きの時間を過ごしました。そして半年後、娘が賢治の学校に通うようになりました。その中で自分の職業もであった英語教師のお話をいただき、今現在英語科の教師として、生徒たちと共に言葉の世界を楽しんでいます。
いつも新しく新鮮に子どもに出会うように、日々心がけています。
何でも聞きます!ロック、ジャズ、クラッシック。歌うのも好きです!

賢治の学校で音楽を担当されている高橋先生と大学の同級生で、髙橋先生の紹介で関わるようになりました。
音楽を通して、生徒が笑顔になるように心がけています。
ショパン

本校の卒業生でした。
現代社会の中で、私たちの立ち位置について、しっかり意識できるような授業づくりをしています。
パンク・ロックです。

きっかけはこの学校の創設者の鳥山敏子さんに誘われたことです。私も昔から学校づくりがしたいこともあって、鳥山さんから誘われたときに「これは自分がやりたかったことだ、今関わるべきだ!」と思い、賢治の学校の学校づくりに参加しました。さらに鳥山先生と2003年にドイツで一年間シュタイナー教員養成ゼミナールを受けました。その時からクラス担任として賢治の学校で日々、子どもたちの育成に励んでいます。
子どもが何を学びたいか、常にそれに答えるように子どもを支えていくことが大切だと思います。それは子どもに読み書きを教えるだけでなく子どもという本を私が読むのです。その姿勢を私は大切にしています。
武満徹さんの曲。特にオーケストラの中に尺八をコラボさせる大作が大好きです。

鳥山先生の新刊「生きる力をからだで学ぶ」を読んだとき、とても興味をひかれました。その前よりシュタイナー教育のことも知り始めていたので、賢治の学校の取り組みをネットで知りました。その後、夫の転勤で愛知県から東京へ引っ越すタイミングで子どもを賢治の学校へ入学させました。
子どもが全身で表す喜びを逃さずキャッチしたいです。
気分によって、洋楽、邦楽問わずいろいろ聴きます。とても幅広いです。最新Jポップから昔の詩ユーミン等まで。

北海道の教員時代に地元の本屋で鳥山先生の「賢治の学校」を購入したのが始まりです。その後賢治の学校を訪れたことがきっかけで、現在同僚の合場義郎氏にワークショップに誘われました。北海道小樽の鳥山敏子のワークショップに参加して、その後運命のように2003年に海を渡りドイツでの教員養成ゼミナールに入学しました。
まっすぐに生きる姿。まっすぐに向かう姿。そしてまっすぐに生徒を愛する姿。
ドリームズカムトゥルー。吉田美和さんの歌です。

自分の子どもの学校を探す中で出会いました。学校祭に訪れて、高等部生徒の佇まいや親たちの明るさ、多摩川を目の前にした風景が印象的でした。
私自身、仕事を持つ親として学童の存在にとても助けられました。
自分も含め、その人らしさの核のようなものが、伸びやかに健やかであれること。
星野源さん。
子どもと一緒に歌うこと。
■オイリュトミーとは?
オイリュトミーとはギリシャ語で「美しいリズム」を意味します。言葉や音楽を身体で表現する、シュタイナー教育の根幹の1つをなす教科です。伸びゆく身体の成長を助け、表現力豊かな人間性を育てます。
■フォルメン線描とは?
フォルメン線描とは、文字や数字の根底にあるフォルム(形)を学ぶ、シュタイナー学校独自の授業です。文字も数字も幾何学もすべてが形からできています。形の感覚を養うことで、その後に出てくる文字や数字の感覚を養う準備ができるのです。

歴史
シュタイナー学校の卒業生として大学で歴史を学び、さらに日本神話を専門とする。日本の京都の大学で研究をつづけ、ドイツに帰国後はクックスハーフェンのシュタイナー学校で高等部の歴史教師として教鞭をとる。現在はシュタイナー教育の高等部の歴史教育の研究を行っている。

物理・教師研修
1955年 ドイツ・カッセル生まれ
カッセルのシュタイナー学校を卒業後、ゲッティンゲン大学で数学と物理を専攻。
1986年よりニュルティンゲンのシュタイナー学校で数学、物理、テクノロジー、幾何学担当、ニュルティンゲン・シュタイナー学校の代表理事でもある。
言語治療者の妻との間に3人の子どもがいる。
エポック授業は物理(光学)。

地理・地学・教師研修
1951年ドイツ生まれ。1973年 大学で生物と地学を学び教員免許習得。その後カッセルのシュタイナー教員養成ゼミナールに入学。シュタイナー学校高等部教員免許習得後はカッセルとハノーヴァーのシュタイナー学校で高等部の教師就任。
1991年からニュルンベルクのシュタイナー学校の高等部の教師として地学、地理、生物を担当。ニュルンベルクではヴィリギリウス・フォーグルと鳥山雅代と共に高等部指導に力を入れる。ニュルンベルク教員養成学校の講師も勤め若い教師の養成にも携わっている。妻と4人の子どもがいる。

文学・外国語教師研修
1963年ベルリン生まれ。アントロポゾフィー医学の父親もとに生まれ、幼いころからベルリン市内のシュタイナー幼稚園、シュタイナー学校で学ぶ。ベルリン大学で文学を専攻したのち、1980年代の後半から、ベルリン・メルキッシュフィアテルシュタイナー学校の設立に関わり、以来同学校で高等部物理学専門の夫とともに、高等部の文学教師と高等部担任として理事としての学校の中心的存在として関わる。
現在ベルリン教員養成の講師としても活躍し、若い高等部教師の育成も務める。

生物・教師研修
1963年北ドイツのキールに生まれる。
1970-1984年ベルリンとシュトゥットッガルトのシュタイナー学校へ通う。
1984年アビトゥーア取得。
1984年-1992年ベルリンの大学で生物と化学を専攻。海水と淡水にさらには環境問題にも取り組む。
1992年よりベルリンのシュタイナー学校で高等部の化学と生物の教科を担当。高等部の生物実習をデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、スコットランドで行なう。
1997年よりベルリン教員養成ゼミナールの高等部の教員養成を担当。主な教科は胎児学と進化論。
現在はベルリン教員養成ゼミナールの代表を務める。

クラス担任教師研修
1952年2月5日 ドイツ・エアランゲン生まれ。エアランゲン大学で社会学と教育学を専攻後、ニュルンベルクのシュタイナー教員養成ゼミナールで教員免許習得。
1979年よりニュルンベルクシュタイナー学校でクラス担任・音楽専科・英語専科を担当。
1984年から理事に就任。1998年からはニュルンベルク教員養成ゼミナールの講師就任。ドイツヴァルドルフ学校連盟のニュルンベルク代表委員。
クラス担任5回目のベテラン教師で生徒からも親からも同僚からも愛される存在。
美術史研究家の夫をもち、3人の子ども(息子2人娘1人)の母親でもある。特技はピアノと合唱、コーラスにも毎週かよう芸術的センスを備えている。

化学・教師研修
1963年ハンブルク生まれ。ベルリンの大学で物理学を専攻。のちにシュタイナー教育と出会い、ベルリンの教員養成を経たのち、ベルリン・ミッテのシュタイナー学校の高等部化学を教える。
のちにヘルムート・エラーが設立に関わった、故郷のハンブルクにあるベルクシュテットシュタイナー学校の高等部化学を担当し、高等部担任として長年シュタイナー教育の高等部化学教育の研究にも関わる。

歴史・教師研修
1982年から現在まで、ニュルティンゲンのシュタイナー学校高等部教師歴史、経済学、国語、演劇論、フランス語、天文学を教える。
ニュルティンゲンシュタイナー学校理事/バーデンヴュッテンブルク州ヴァルドルフ学校連盟の代表理事/シュトゥットゥガルトのシュタイナー教員養成ゼミナールの高等部専門講師/シュトゥトゥガルトのシュタイナー学校国内研修会議の主導実行委員就任/ヨーロッパシュタイナー学校連盟の大学資格制度改定実行委員会委員/1995年からワルシャワのシュタイナー学校設立委員ドイツ支部代表とシュタイナー教員養成ゼミナールワルシャワの講師および教師研修実行委員
現在「東京賢治の学校 高等部」責任者を兼任2008年度より自由ヴァルドルフ連盟総理事。